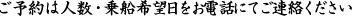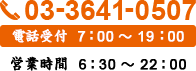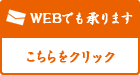深川の歴史

Home深川の歴史
江戸歓進相撲発祥の地
江戸歓進相撲とは
富岡八幡宮は江戸勧進相撲発祥の地として有名です。
江戸時代の相撲興業は京・大阪からはじまりますが、 トラブルが多くしばしば禁令が出ていました。
その後禁令が緩み、貞享元年(1684)幕府より春と秋の2場所の勧進相撲が許されます。
その地こそが当宮の境内だったのです。
以降約100年間にわたって本場所が境内にておこなわれ、その間に定期興行制や番付制が確立されました。
そののち本場所は、本所回向院に移っていきますが、その基礎は当宮において築かれ、現在の大相撲へと繋がっていくことになります。
富岡八幡宮
東京都江東区富岡1-20-3
TEL 03-3642-1315
- 【東京メトロ東西線】
- 「門前仲町」駅より徒歩3分
- 【東京駅丸の内北口発】
- 東22・東20系統 錦糸町駅前行「富岡一丁目」下車 徒歩2分
錦糸町駅前発 都07系統 門前仲町行「富岡一丁目」下車 徒歩2分
※富岡八幡宮ホームページより転載

深川八幡祭り
江戸の粋を今に伝えるお祭り
富岡八幡宮の例祭は8月15日を中心に行われます。
俗に「深川八幡祭り」とも呼ばれ、赤坂の日枝神社の山王祭、神田明神の神田祭とともに「江戸三大祭」の一つに数えられています。
3年に1度、八幡宮の御鳳輦が渡御を行う年は本祭りと呼ばれ、大小あわせて120数基の町神輿が担がれ、その内大神輿ばかり54基が勢揃いして連合渡御する様は「深川八幡祭り」ならではのものです。
深川のお祭りは「ワッショイ、ワッシヨイ」の伝統的な掛け声と「水掛け祭」の別名通り、沿道の観衆から担ぎ手に清めの水が浴びせられ、担ぎ手と観衆が一体となって盛り上がるのが特徴で、江戸の粋を今に伝えるお祭りとして、多くの人々によって大切に受け継がれています。
※富岡八幡宮ホームページより転載

担ぎ手と観衆が一体となって盛り上がるのが特徴。
深川縁日
数多くの露天が立ち並び夏祭りのような賑わい
門前仲町交差点の辺りから富岡八幡までの永代通りの北側歩道および深川不動尊の参道にて毎月1日、15日、28日に行われます。
数多くの露天が立ち並び夏祭りのような賑わいが1年を通して感じる事が出来ます。
午前中から露天の設営が始まり、昼過ぎになると多くの露店が軒を連ねます。「たこ焼き」「あんず飴」「わた飴」「カルメ焼き」等の懐かしい食べ物やさんや「占いの本」「衣料品」「鉢植え」等の物販店が数多く出店する。
※富岡八幡宮ホームページより転載

1年を通してお祭り気分が味わえます!